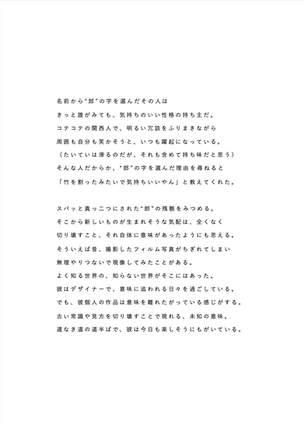不字の美
鈴木 雄飛
名前を10回書くと、
自分のなりたい姿がみえてくる。
(以下、序文より抜粋)
人は“名前の通りの人生”を歩むという。
名前は親からもらう最初のプレゼントであり
こんな子に育ってほしいという願いを生きていく。
学校では名前の正しい意味とその書き方を教わり
誰が書いても同じ形になるように刷り込まれていく。
しかし、やがて人は、自らの名前を崩しはじめる。
アンケート用紙や宿泊者名簿の記入欄。
宅配の受け取りや領収書のサインに至るまで。
名前は「人生で最もたくさん書く文字」だからこそ
自分さえ読めればいい、自由な形へと変貌を遂げていく。
それは文字にあって文字にあらず。不字である。
不字は暗示しているのではないだろうか。
その人にとっての“ほんとうに自由な生のかたち”を。
人はいつだって自由を探し続けている。
それが何なのか、わからなくて、わかりたくて
親や社会から与えられた型を飛び出して生きていく。
名前は、そんな自分の分身でもある。
誰かと比較することなく、ただ自分が気持ちよく
繰り返し名前を書くなかで到達する自由の形がある。
大切な人のそれについて、一緒に考えてみたいと思った。
自由な姿形がいちばん美しいと、僕は思うから。
---
(以下、あとがきより抜粋)
|柳宗悦の民藝運動
不字という着想は民藝運動の父として知られる柳宗悦(1889-1961)から得ています。柳が生まれたのは明治維新に日本が揺れていた時代。武器から食器に至るまで、様々な西洋文化が入ってくる中で、劣った日本文化を刷新しようという機運が高まっていました。そこに反発したのが柳です。西洋の洗練された美のデザインと比較して、日本の美は確かに不揃いで土着的です。でも、美しいことに変わりはない。器をはじめとした生活用品を作る人の多くは、学校に通わず、生活に必要なものだけを大量に作り続ける日々。つまり、何が美しくて醜いのかも知らぬまま、頭ではなく手を動かし続けました。
しかし、だからこそ“こうすれば美しくなる”という西洋の知識と作為に満ちた美とは異なる美が現れる。柳はこれを「不二(ふじ)の美」と呼び、日本の工藝品を民藝という言葉で結晶化しました。昨今日本では民藝ブームですが、柳が始めた民藝運動によって、今も全国各地で昔ながらの工藝品が作られています。
|名前は民藝的である
この民藝的な営みは、現代人の生活において、実は今も連綿と続いているのではないか。そう考えて着目したのが「名前」です。人は一生をかけて名前を大量生産します。文字の形が美しいかどうかなんて、いちいち気にしません。つまり、西洋的な美が根づいた今でも、名前を書くことに関しては、美醜へのとらわれを抜け出して「不二の美」が出現しうるのではないか。
柳のいう「不二の美」の不二とは仏教の概念です。私とあなた。自分と自然。2つあるものをそれぞれ独立した存在として現代人は認識しますが、これは西洋哲学の生み出した主体と客体という概念から出発した考え方です。東洋の人は長らく、そのようには考えませんでした。動植物を食べて生きる我々はどこからが自分か。苦しみというものは世界に独立して存在するのか、それとも自分の生み出す幻なのか。2つあるように見えるものは、実はひとつで、それを分けて考えてしまうからおかしなことになるのではないか。この「2つあるようで2つにあらず」の考え方を「不二」と呼び、仏教の中核概念を成しています。
柳は日本の美の思想的な源泉を仏教に求め、民藝の中に見出しました。美醜へのとらわれのない民藝の作者は、土の声を聞き、器と一体化します。不二の美へと至るのです。
|不二の美へと至る不字
不字という造語は、この不二をもじっています。名前に込められた願いや意味と、自分という固有の存在。その2つが、名前を何度も書く中で一体化し、不字というかたちで不二の美へと至るのではないか。
柳は不二に到達した美を「自由の美」だとも語っています。2つの間に一切の境界がないからこそ、どこまでも自由なのです。であるならば、名前が不字へと至るとき、そこには、その人にとっての自由さが美しい姿形をともなって顕現するはずです。そこまで思い至ったとき、不字という概念が、ひらりと僕の手元に舞い降りてきました。詳細は本編をご覧いただければと思います。